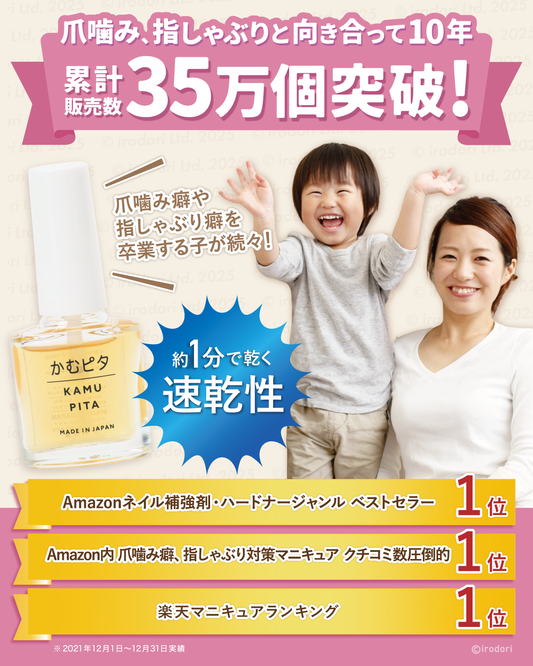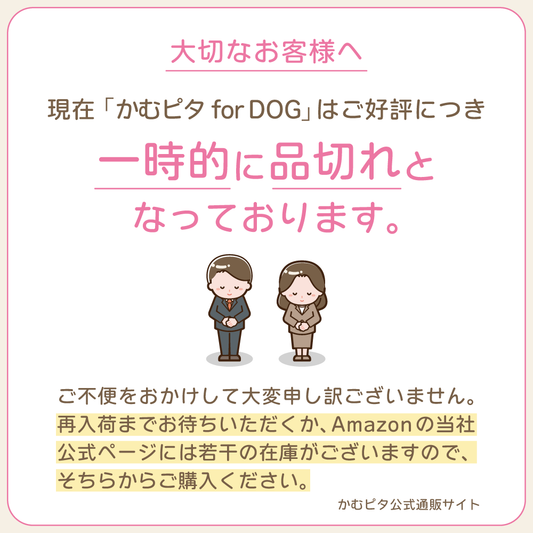子どもの爪噛み、叱っていませんか?ついやってしまう 「逆効果の対応」とは?
なんで、やめてほしいのにやめてくれないの?
「また噛んでる!」 気づくたびについ注意してしまう——そんな日々を過ごしていませんか? 爪噛みをする子どもを見ると、「恥ずかしいから」「汚いから」「病気になったら困るから」と、つい強く止めさせたくなりますよね。
けれど実は、親がよかれと思って取る対応が、爪噛みを長引かせる原因になることがあります。
この記事では、ついやってしまいがちなNG対応と、その裏にある子どもの心理、そして今日からできる見直しポイントをお伝えします。
----------------------------------------------------------
■ 爪噛みをやめさせたい親がやりがちなNG対応
----------------------------------------------------------
①「やめなさい!」と叱る・注意を繰り返す
もっとも多いのが、繰り返し叱ったり、口うるさく注意したりするパターンです。
しかしこれは、子どもにとって「噛む=注目される行動」になってしまうことがあります。 叱られてもやめられないのは、「不安」「退屈」「緊張」などの気持ちを、噛むことで落ち着けているから。 心を整える手段を奪われると、余計に噛みたくなるのです。
② 「赤ちゃんみたい」「恥ずかしいよ」と言ってしまう
親の言葉は子どもに深く残ります。 恥ずかしい・ダメなこととレッテルを貼ると、自己否定感を強め、ストレスが増加します。 そのストレスを発散するために、再び爪を噛む——という悪循環に陥りやすいのです。
③ 無理に「やめさせよう」とする
「絶対やめさせたい」という強い思いがあるほど、親の表情や声にプレッシャーが滲みます。 子どもはその“圧”を敏感に感じ取り、緊張や不安が高まります。 その結果、爪を噛むことで安心しようとするのです。 やめさせるよりも、“落ち着ける方法”を一緒に探すことが大切です。
■ 正しい対応の第一歩は「観察」と「理解」
やめさせるために必要なのは、行動を止めることではなく、原因を見つけることです。 「どんなときに噛むのか」「どんな表情をしているか」を静かに観察してみてください。 テレビを見ているとき? 叱られたあと? 眠いとき? 退屈そうなとき? そこには必ず“理由”があります。 それがわかると、爪噛みを「悪い癖」ではなく、「サイン」として受け止められるようになります。
【まとめ】
やめさせるより、「支える」へ。
爪噛みは、心が少し疲れたときに出るサイン。 それを責められるよりも、理解され、安心できる環境が整うと、改善されることがあります。 親が変われば、子どもの行動も変わります。
今日からは「やめさせる」ではなく、 「どうしたら安心できるかな?」と寄り添う姿勢に変えてみましょう。 焦らず、少しずつ。 それが、爪噛み卒業へのいちばんの近道です。
爪噛み 子ども 親 対応 爪噛み 叱る 逆効果 爪噛み やめさせたい 方法 子ども 爪噛み 心理 爪噛み やめさせる 親の対応